
Z900RSをフェンダーレス仕様にカスタムしたいと考えている方にとって、フェンダーレスキットの選び方や車検に対応するための基準、さらには泥はねへの対策は欠かせない要素です。リアフェンダーを取り外すことでスタイリッシュな外観を実現できますが、同時にバイクの全長や保安基準に関する注意点も押さえておく必要があります。
本記事では、z900rsのフェンダーレスキットの特徴や比較ポイント、バイクのフェンダーレスによる車検への影響、フェンダーアームで調整するナンバープレートの角度といった技術的な面まで、実用的な情報を網羅。
さらに、フロントフォークの調整方法やリンクプレート交換による泥はねリスク、z900rsの電源取り出しハーネス使用時の防水対策など、快適なカスタムを実現するノウハウも紹介します。フェンダーレス化に踏み出す前に、ぜひ一読してみてください。
Kawasaki Z900RS | アイコニックなレトロスポーツモデル↗
記事のポイント
- フェンダーレスキットの選び方と車検対応の基準
- バイクのフェンダーレス化が車検に与える影響
- ナンバープレート角度の調整方法と注意点
- 泥はねの原因と対策パーツ・調整方法の紹介
- 実用性と見た目を両立するカスタムの工夫
Z900RSのフェンダーレスにおける車検対応の基準と選び方

フェンダーレスキットの特徴と選ぶ際のポイントについて
Z900RSにおけるフェンダーレス化とは、バイクの後部にある大型の純正フェンダーを取り外し、よりコンパクトな形状のカスタムパーツに置き換えるカスタマイズのことを指します。これにより、車体後部がすっきりとした印象となり、洗練されたスタイルを演出できます。特にZ900RSのようなネオクラシックデザインのバイクでは、レトロな雰囲気を損なうことなく、モダンなテイストを加えることが可能です。
フェンダーレスキットには、ナンバープレートステー、LEDライセンスランプ、リフレクターなどが含まれており、それぞれが安全性や法令適合性に配慮して設計されています。たとえば、キジマ(KIJIMA)製のフェンダーレスキットは、ナンバープレートの取付角度が車検対応である40度以内に調整可能であり、視認性の高いLEDライセンスランプとリフレクターを標準装備しています。
選定の際には以下のポイントに注意する必要があります。
| 選定ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法規対応 | ナンバープレートの角度が40度以内であること、リフレクターとナンバー灯の装備 |
| 耐久性 | スチールやABS樹脂などの素材を使用し、長期間の使用に耐える構造 |
| デザイン性 | バイクの外観を損なわない、スタイリッシュなフォルム |
| 防水性 | 雨天時に備えた配線部分の防水加工があるか |
| 取り付けのしやすさ | 説明書の分かりやすさ、DIY向けかどうか |
特に、DIYでの取り付けを想定する場合は、パーツの精度や付属する取り付けガイドの明確さがカスタム成功のカギとなります。複数メーカーの製品を比較し、レビューを参照することで、より納得のいく製品選びが可能です。
バイクのフェンダーレスが車検に与える影響と保安基準の注意点
フェンダーレス化に際して最も注意すべきは、日本の道路運送車両法に基づく保安基準の適合性です。フェンダーは本来、泥や小石の跳ね上げを防ぐために設計された重要な部品であり、その取り外しや変更が安全基準を損なうものであってはなりません。
具体的には、以下のような保安基準が存在します。
- ナンバープレートの取付角度:上向き40度、下向き15度以内
- ナンバー灯の装着:夜間にナンバープレートが明瞭に確認できる明るさを保持すること
- リフレクターの装着:後方からの視認性を確保するため、中央よりに配置すること
このように、フェンダーレスキットを導入することで上記の基準を満たさない場合、車検には通りません。特に、安価な非純正品や海外製パーツには注意が必要であり、国内の保安基準に適合していない場合があります。車検対応品であるかどうかは、製品説明やメーカー公式サイトなどで事前に確認しましょう。
さらに、灯火類の位置変更やフレーム加工を伴うカスタムを行う場合、構造変更申請が必要になることもあるため、事前に整備士や車検対応専門店に相談することが望ましいです。
フェンダーアームによるナンバープレート角度調整の方法とは
フェンダーレス化によってナンバープレートの角度が変わると、上述の保安基準に抵触する可能性があります。これを回避する手段として活用されているのが「フェンダーアーム」です。フェンダーアームはナンバープレートのステーと車体の間に設置され、角度を適正に調整するための補助部品です。
多くのフェンダーレスキットには、あらかじめ40度以内に設定された角度のナンバーステーが組み込まれており、専用のアームや角度調整機構が備わっています。以下に角度調整の工程を示します。
- フェンダーレスキットの台座にナンバーステーを仮留めする
- プレートを固定し、実際の角度を確認する
- 付属の調整ボルトやスペーサーを使用し、角度を微調整する
- 最後に締め付けを行い、強固に固定する
注意点としては、角度の測定時に必ず地面と垂直の状態で測定すること、また調整後にプレートがしっかりと固定されているかを確認することが挙げられます。走行中の振動によりナンバープレートが動いたり落下する危険を回避するためにも、丁寧な取り付けが重要です。
また、角度を固定する構造により、長期使用後に緩みが生じないよう定期的な点検を行うことも大切です。
純正フェンダーとカスタムパーツの比較による適合性の違い
純正フェンダーは、メーカーが安全性・耐久性・法令遵守を前提に設計しているため、車検における適合性が完全に保証されています。一方で、デザイン性には限界があり、Z900RS本来のクラシックな美しさを活かしきれていないという声も多く聞かれます。
一方、カスタムパーツとしてのフェンダーレスキットは、スタイリッシュな見た目と軽量化を実現できますが、製品によって適合性や信頼性に差があります。
| 項目 | 純正フェンダー | フェンダーレスキット |
|---|---|---|
| 法令適合性 | 完全適合 | 製品によって差がある |
| デザイン性 | 標準的、実用重視 | スタイリッシュで個性的 |
| 重量 | やや重い | 軽量な製品が多い |
| メンテナンス性 | 比較的高い | 配線や防水対策に注意が必要 |
| 車検適合性 | 問題なし | 製品選びに注意が必要 |
このように、適合性を担保するためには「車検対応」の明記がある製品を選ぶことが大切です。また、適合確認済みの車種専用キットを選ぶことで、加工の必要がなく、取り付け後の不具合も回避できます。
車検対応マフラーとフェンダーレスキットの組み合わせ方
Z900RSをカスタムする際、多くのユーザーがフェンダーレスと合わせてマフラーの交換も検討します。スタイルの統一感を重視するためですが、マフラーもまた厳格な保安基準が存在するパーツの一つです。
特に注意すべき点は以下のとおりです。
- 音量規制の適合:加速騒音試験に適合している必要があります
- エンジン型式との適合性:政府認証マフラーかどうか
- マフラー出口とナンバープレートの位置関係:排気ガスが直接プレートに当たらないよう配慮が必要
車検対応マフラーを選ぶ際には、JMCA(全国二輪車用品連合会)認証がある製品を選ぶと安心です。フェンダーレスキットとマフラーの干渉がないかも重要なチェックポイントであり、装着後のクリアランス確認が必須です。
全長規定に適合させるための車検対策とそのチェックポイント
フェンダーレス化によって、バイク全体の全長が短くなる場合があります。これは一見良いことに見えるかもしれませんが、車検においては「車両の構造等に変更がある」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
車検における全長は、前端から後端までの長さを計測し、車検証に記載された数値との差が一定以上あると「構造変更申請」が求められます。通常、その差が±3cmを超えると申請対象になるため、フェンダーレス化によりリア周りが大幅に短縮された場合は、再測定の必要があります。
チェックポイントとしては以下の通りです。
- フェンダーレスキット装着後の全長測定
- マフラーやキャリアなど他パーツの出っ張りを考慮する
- ナンバー角度調整による後端長の変化に注意
もし全長が基準を超えて変更された場合は、最寄りの陸運局にて構造変更申請を行い、新たな記載内容の車検証を取得する必要があります。この手続きを怠ると、車検を通過できないだけでなく、公道走行も違法となるため十分な配慮が必要です。
Z900RSのフェンダーレスによる泥はね問題とその対策方法

Z900RSのカスタムにおいてフェンダーレス化は非常に人気がありますが、同時に避けられないのが「泥はね」問題です。リアフェンダーの本来の役割は、タイヤが巻き上げる水や泥を車体やライダーに飛び散らないように防ぐことにあります。これを取り外してしまうことで、雨天時や濡れた路面を走行する際に背中や車体が泥だらけになることが少なくありません。
Z900RSのようなクラシックスタイルのバイクでは、見た目の美しさと実用性のバランスが求められます。そのため、フェンダーレス化に伴う泥はね問題をどう解決するかが重要です。以下で各種対策と工夫について詳しく解説していきます。
フロントフォークの調整による泥はね軽減の工夫について
泥はねの対策として真っ先に検討したいのが「フロントフォークの調整」です。Z900RSでは、フロントフォークの突き出し量を調整することで前傾姿勢を強めることが可能です。この調整により、リアの車高がわずかに上がり、泥が跳ねる角度が変わることで、結果的に背中への泥はねが軽減されます。
具体的な方法としては、以下のようなステップで実施されます。
- トップブリッジの固定ボルトを緩め、フォークの突き出し量を調整
- 最大でも5mm以内の範囲で調整する(大きな変更はハンドリングに影響を与えるため)
- 調整後は必ずトルクレンチで指定トルクにて固定する
この調整によって、バイク全体の前後バランスが変化し、後輪の跳ね上げ角度が変わることで、フェンダーがない状態でも泥の飛び方が制御されます。ただし、サスペンションセッティングや走行スタイルによっては逆効果となる場合もあるため、事前の試走や微調整が必要です。
フェンダーレスキットの種類ごとの泥はね性能の比較
フェンダーレスキットにはさまざまな種類があり、その設計や材質によって泥はねに対する性能も大きく異なります。ここでは代表的なフェンダーレスキットを比較し、それぞれの泥はね対策効果について解説します。
| メーカー | 主な素材 | 特徴 | 泥はね対策効果 |
|---|---|---|---|
| KIJIMA | スチール製 | ナンバー灯とリフレクター標準装備、防水性に優れる | 中程度:配線部の防水処理あり |
| DAYTONA | アルミ製 | 車検対応、軽量で錆びにくい | 中〜高:リフレクター位置が高めで泥の跳ね返りが減少 |
| ARCHI | ABS樹脂 | ロングテールデザイン、配線が見えない設計 | 高:車体後部の泥はねが少ない |
| アクティブ | スチール製 | 高剛性、プロ向けの設計 | 低〜中:デザイン重視で泥除け効果は限定的 |
このように、フェンダーレスキットは単なる外観だけでなく、泥はね防止機能にも注目して選定する必要があります。特に、ロングテール形状やナンバー位置の高さは重要な要素であり、視認性と実用性の両立を図ることが大切です。
リンクプレート交換によるリア下がりと泥はねリスクの関連性
Z900RSの足回りカスタムのひとつに「リンクプレートの交換」があります。これはリアサスペンションのリンク比を変更し、乗り心地やスタイルを変化させるカスタムですが、リア下がり(ローダウン)状態になると、フェンダーの位置とタイヤの間隔が狭まり、泥の巻き上げが車体に直撃しやすくなります。
リンクプレートを変更すると、以下のような影響があります。
| 状態 | 効果 | 泥はねへの影響 |
|---|---|---|
| ノーマルリンク | 標準的な車高 | 泥の飛散角度が広くなる |
| ローダウンリンク | リア下がり、足つき改善 | 泥がテールライトや背中に集中しやすくなる |
| ハイリンク | リア上がり、スポーツ志向 | 泥が後方へ抜けやすくなるがスタイルに影響 |
このように、リンクプレート交換は乗車感を大きく変える反面、泥はねのリスクにも直結するため、フェンダーレス仕様での導入時には泥除けパーツとの併用が強く推奨されます。
電源取り出しハーネス使用時の防水と泥はね対策の実践法
フェンダーレス化と同時にテールランプやナンバー灯に電源を供給する必要があり、その際に使われるのが「電源取り出しハーネス」です。このハーネスはリアシート下のカプラーから分岐して使うことが一般的ですが、配線の露出部から水分が浸入し、ショートや腐食の原因となるリスクがあります。
防水と泥はね対策として以下の方法が効果的です。
- 配線の保護:電工テープや熱収縮チューブで結線部を密閉する
- ジョイント部のシーリング:防水グリスやシリコンスプレーを使用
- ステー部分へのシリコン充填:泥の侵入を物理的に防ぐ
特に、雨天走行を想定する場合、シート下やカウル内に防水対策を施すことで、長期的なトラブルを防止できます。
フェンダーの取り外しが泥はねに及ぼす影響とその解決策
リアフェンダーを取り外すことで最も顕著に現れるのが「背中への泥はね」です。通常、純正フェンダーはタイヤとテールランプの間に存在し、泥や水滴を跳ね返す役割を果たしています。これを取り外すと、テールランプ、ナンバープレート、そしてライダー自身が泥の直撃を受けることになります。
この問題への対処法としては以下のような手段が有効です。
- ロングインナーフェンダーの装着:タイヤ後方まで延びた設計で、泥の飛散を防止
- リアスポイラー形状のカスタムパーツ追加:跳ね上がりを分散
- ナンバー裏側への泥除けプレート設置:視覚的なカスタム効果もあり
これらの対策を組み合わせることで、フェンダーレスでも実用性を損なわずに快適な走行が可能になります。
アルミプレートなどを活用した自作による泥除け方法
市販のフェンダーレスキットが泥除け機能に不安を感じる場合、DIYによる自作泥除けも選択肢として非常に有効です。特に、軽量で加工しやすいアルミプレートは、見た目と実用性の両立が可能な素材として人気があります。
自作の泥除けの作り方は以下の通りです。
- アルミ板をナンバーサイズにカット
- 下部に向かって湾曲させ、タイヤ方向に延ばす
- ステーやボルトでナンバー裏に固定
- 防振ゴムやスポンジを挟み、振動吸収を図る
この方法で、泥の巻き上げを物理的に遮断し、かつコストを抑えたオリジナルカスタムが可能です。見た目にもスタイリッシュな仕上がりになるため、フェンダーレスと調和したカスタムとして多くのライダーに支持されています。
総括:Z900RSフェンダーレスの車検対応と泥はね対策についての本記事ポイント
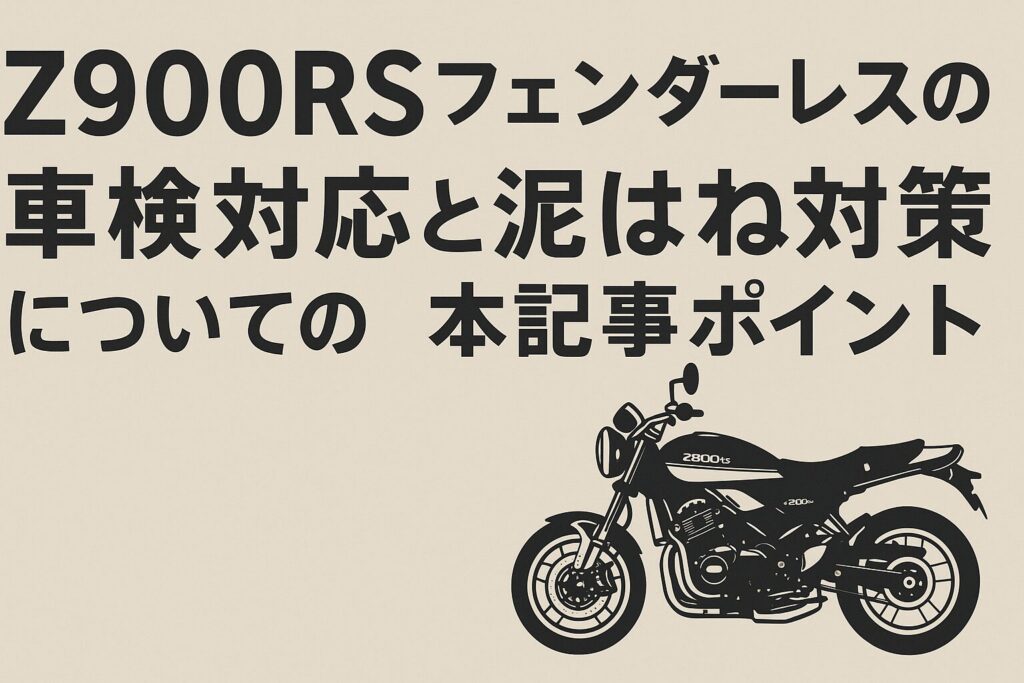
Z900RSにおけるフェンダーレスカスタムは、その美観と個性を引き出す魅力的な選択肢である一方で、車検対応の法的要件や実用面での泥はね問題など、慎重な検討が求められる要素も多く存在します。本記事では、フェンダーレス化に伴う基準と注意点、また泥はね対策における具体的な方法について詳しく解説してきました。以下に、本記事の要点を総括としてリスト形式でまとめます。
✅ フェンダーレスキット選びのポイント
- ナンバープレートの角度は「上向き40度以内・下向き15度以内」を厳守
- LEDナンバー灯と反射板(リフレクター)の装備が車検対応の必須条件
- 耐久性・防水性・デザイン性に優れた製品(KIJIMA、DAYTONAなど)が推奨
- ボルトオン設計でDIY取り付けしやすい製品を選ぶと安心
✅ フェンダーレス化が車検に与える影響と対策
- 灯火類の再配置は保安基準に基づき適切に行う必要あり
- ナンバー角度が基準を超えると車検不合格の可能性がある
- 全長が3cm以上短縮されると構造変更申請が必要
✅ マフラーとフェンダーレスの組み合わせに関する注意点
- 車検対応マフラー(JMCA認定)を選び、排気がナンバーにかからないよう設置
- ナンバーステーやフェンダーキットとの干渉に注意
✅ フェンダーレスによる泥はねリスクと対策
- フロントフォークの突き出し調整でリアの跳ね上げ角度を最適化
- インナーフェンダーをロングタイプに交換して泥よけ効果を強化
- アルミプレートなどを活用した自作泥除けの導入が有効
- 電源ハーネス部の防水処理も忘れずに実施
✅ 車体セッティングによる泥はね影響の違い
- リンクプレートの交換によるリア下がりで泥はねリスクが増大
- ハイリンク化で後方への泥飛びを分散できる場合もある
Z900RSのフェンダーレス化は、単なるスタイルアップにとどまらず、安全性と実用性を伴う重要なカスタム作業です。車検に適合しながら、快適な走行を実現するためには、製品選定から取り付け、そして走行後のメンテナンスまで、トータルでの対策が求められます。
本記事を通じて、フェンダーレスに関する適切な知識と対策を身につけ、安全かつスマートなZ900RSライフを楽しんでいただければ幸いです。






コメント